着物で大江戸散策パート3です。
今日は神田をご案内したいと思います。
「宵越しの銭は持たない」
「火事と喧嘩は江戸の華」
江戸っ子のイメージってこんなんですよね(笑)。
そんな江戸っ子のなかの江戸っ子が、
住んでいたといわれるのが神田です。
広沢虎造の浪曲「石松三十石船」のセリフにもある、
「江戸っ子だってね」「神田の生まれよ」
のやり取りにみられるように、
江戸時代は神田はブランドだったんですね。
神田は徳川家康が江戸に入植した際に、
丸の内から日比谷にかけてあった、
日比谷入江を埋め立てる為、
(現在の日比谷公園や新橋周辺)
神田山を切り崩したことから始まります。
以前ブログに書いた銀座も、
この一大プロジェクトにより、
埋め立てられて今の形になりました。
詳しくは下記のリンクをご参照ください。
切り崩された神田山は、
現在の駿河台あたりでした。
駿河台という地名は、
徳川家康の家来の駿河出身者が、
屋敷を多く構えたことから名付けられました。
駿河台から小川町あたりまでの神田は、
武家地が母体になっていて、
一方内神田あたりのは町人街があり、
神田は武家が住む武家地と、
町人街で大きく2つに分かれていました。
神田の名所
神田明神は日本三大祭りの一つである、
神田祭を取り仕切る神社です。
神田祭については以前書いた、
も見てみてください。
神田明神は江戸城の表鬼門守護の場所である、
現在の場所に遷座し、
「江戸総鎮主」として、
幕府や庶民の崇敬を集めてきました。
明治維新になり神田神社に、
正式名称を変えましたが、
神田明神の方が相応しい気がします。
神保町の世界最大の古書店街は、
明治維新になり多くの学校
(大学南校(現東京大学)や華族学院(現学習院) )が、
駿河台周辺の武家屋敷跡地などに集まり、
それに伴って形成されました。
ギリシャ正教の聖堂のニコライ堂は、
国の重要文化財にも指定されていて、
日本最大の正教会の聖堂です。
湯島聖堂は5代将軍徳川綱吉が建てたものです。
湯島天満宮とともに年中を通して、
合格祈願の為の参拝が絶えません。
現代の神田
明治維新後の明治11年に神田地域は、
神田区と呼ばれるようになりましたが
1947年に麹町区と合併し千代田区となりました。
現在神田○○町と呼ばれる地域が多いのは、
合併する際に神田の地名を惜しむ人が多かったため、
行政側がその声に応えたものです。
駿河台周辺は東大や学習院は、
別の場所に移動しましたが、
現在も明治大学や日本大学があります。
内神田周辺はオフィス街になっていて、
ビジネスマンの街になっています。





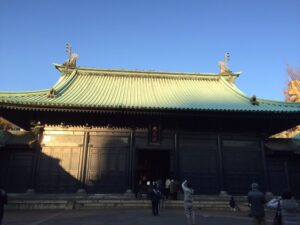
コメント